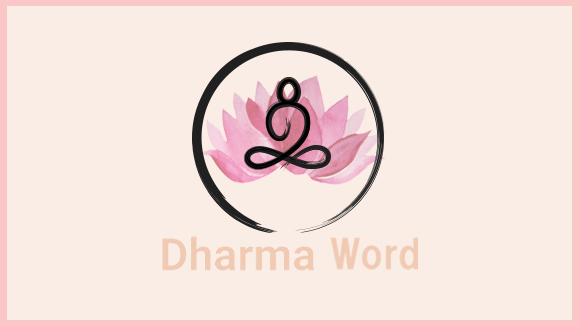庭野日敬法話選集_別巻_00_00_第二回アジア宗教者平和会議〈ニューデリー〉開会の挨拶(IARF)世界大会〈オランダ〉記念講演〈プリンストン〉開会合同礼拝式の挨拶-0005
別巻_第二回アジア宗教者平和会議〈ニューデリー〉開会の挨拶(IARF)世界大会〈オランダ〉記念講演〈プリンストン〉開会合同礼拝式の挨拶
1 ...第二回アジア宗教者平和会議「ニューデリー」開会の挨拶 アジア宗教者平和会議議長 庭野日敬 本日、ここに多くのご来賓をお迎えし、第二回アジア宗教者平和会議を開催するに当たり、ごあいさつの機会をお与えくださいました会長、議長ならびに皆さまにあつく、お礼を申し上げる次第でございます。 加えて、この会議準備のために長い間、ご努力くださいましたインドの皆さま…