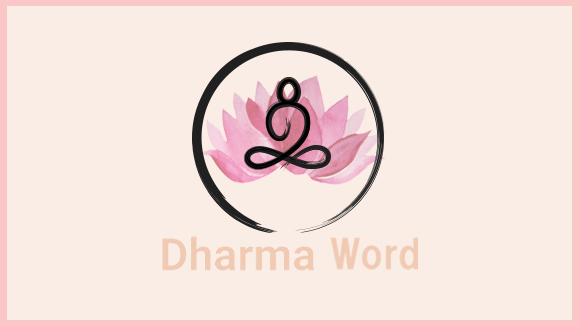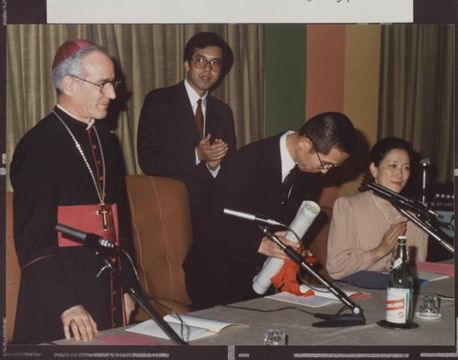経典のことば58
聞(ぶん)をもってのゆえに大涅槃を得るにあらず、修習をもってのゆえに大涅槃を得。(大般涅槃経巻二五)
経典のことば59
心に大歓喜を生じて 自ら当に作仏すべしと知れ
(法華経・方便品)経典のことば61
其の国の中間幽冥の処、日月の威光も照すこと能わざる所、而も皆大に明らかなり。其の中の衆生各相見ることを得て、咸(ことごと)く是の言を作(な)さく、此の中に云何(いかん)ぞ忽ちに衆生を生ぜる。
(法華経・化城諭品)経典のことば62
是の人は少欲知足にして能く普賢の行を修せん
(法華経・普賢菩薩勧発品)経典のことば63
我神力を以て仏を供養すと雖(いえど)も身を以て供養せんには如(し)かじ。
(法華経・薬王菩薩本事品)経典のことば64
能く衆生をして歓喜し礼して、心を投じ敬(うやまい)を表して慇懃(おんごん)なることを成ぜしむ
(無量義経・徳行品)経典のことば65
観音妙智の力 能く世間の苦を救う
(法華経・観世音菩薩普門品)経典のことば66
観世音浄聖は 苦悩死厄に於て 能く為に依怙と作(な)れり
(法華経・観世音菩薩普門品)経典のことば67
忍辱の地に住し、柔和善順にして卒暴ならず、心また驚かず
(法華経・安楽行品)経典のことば68
煩悩ありと雖(いえど)も煩悩なきが如く、生死に出入すれども怖畏の想(おもい)なけん
(無量義経・十功徳品)経典のことば69
未だ自ら度すること能わざれども、巳に能く彼を度せん
(無量義経・十功徳品)経典のことば70
諸仏は五濁(じょく)の悪世に出でたもう。所謂(いわゆる)劫濁・煩悩濁・衆生濁・見濁・命濁なり
(法華経・方便品)